心の一名山
美少年の山「天山」1046m
佐賀県小城郡小城町/多久市/東松浦郡厳木町/佐賀郡富士町
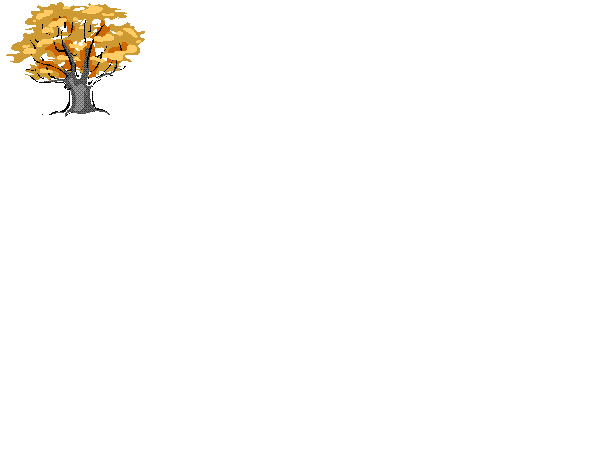 井手敏博
井手敏博
|
野田敬一君を悼む
今年3月6日畏友野田敬一君が急逝された。この日は日曜日で、私はさいたま緑の森博物館の「狭山丘陵に春を探す」自然観察会に参加していた。この日奄美にも雪が降ったという戻りの寒波が全国を襲い、ゴム長を通して足がかじかむ寒い朝だったが、春は確実に萌え出していた。その里山を歩いているさなかに私の携帯電話が鳴り母の死の報がもたらされた。気が動転してそこから私の記憶は途切れ途切れとなるが、いま思えば野田君が逝ったのは大きなトランクを引いて羽田に急ぐ電車の中から、私が呆然と外を見ていた時刻ごろだったのだろうか? 母と同じ日にみまかったことで、彼とのえにしもまた奇しきものとなった。誕生日だって覚えている、昭和24年1月1日だ。「秀吉と一緒だ」と小学生の野田君が言ったものだ。お互いこましゃくれて、かわいくない子どもだったな。 小学校から高校までの12年間は多感で、生物としての成長と目覚めの時期であり、筆舌に尽くせない思い出を共有するものだ。その友の突然の喪失は、ボディブロウのようにじわじわと、私の余生にダメージを与えていくに相違ない。もはや「残躯天の赦すところ、楽しまざるをこれいかんせん」を詠じてともに杯を挙げることもできなくなった。 その多くの思い出のひとつに天山への登高がある。キスリングのパッキング、山の挨拶、焚き火の始末、さまざまの山の作法を最初に教えてくれたのは彼だった。春夏秋冬しょっちゅう天山には行ったが、一緒に行った相手の筆頭もまた彼だった。彼はいなくなったが、共有した多くの美しいシーンの記憶を私の脳はまだ保っているのである。 いまだきちんとした追悼の文を草する気持ちに至らず、とりとめもないことを書いている。以下の文は数年前に山の会の機関誌に寄稿した「私の一名山」の一篇であるが、いま野田君の、いや敬ちゃんとの山旅の追憶として掲載することにする。 敬ちゃん、また一緒に登ろうな! あのナンセンスな笑い話に哄笑しながら。 (2005.11) |

緒言 一名山はあるか
百名山があれば一名山があっても不思議ではないが、人生の峠をすぎたからといってここで一名山を決めなければならない理由はなかろうと思う。もし一名山を、人生という航路の中で見つけることのできた最愛の人と同じものだと考えれば、軽々しくは決められない、幸福な結婚とはウェディングベルを聞きながら実感するものではなく、この世におさらばするときに思うことができるかどうかなのである。適当ではない比喩をもって語れば、20日間で百名山を征服した外国人の物語を読むと、百人斬りに落花狼藉された大和撫子を思わせる。
ということで「私の一名山」は未定なのであるが、そんな生意気が通る世の中ではない。オニさんやクマさんに叱られたり鉄砲玉が飛んでくるのも怖いから、課題に応えるについては有力候補を記して代えることとする。
天山―その大仰な山名
天山は佐賀県小城郡小城町、多久市、東松浦郡厳木(きゅうらぎ)町と佐賀郡富士町の境に位置し、県中央部にあって佐賀平野の北を画すどっしりとした山である。頂稜部は約1kmもつづくなだらかな草原であり、山体は東西4kmにも及ぶ。標高は1046m、前衛のへだてる山はなく平野にその姿をそのままさらしている。そのやさしい山容は大きな丘陵のようであり、なんとなく安心感を与えてくれる肥前の名山である。
そんなことより驚くべきはその大仰な名前であろう。ふつうの日本人にとって天山はなじみのある山名ではあるが、それはあのシルクロードの天山北路・天山南路で人口に膾炙している遥か西域の雪を戴いた重畳たる山脈のことである。今なお多くの未踏峰を抱える6000mをこす秘境の峰々は(まだ行ったことはないが)天を支え地に蟠り、天に至る山と呼ぶにふさわしいように思う。
ああそれなのに、私のかわいい天山はたかが1000mちょっとの分際で畏れ多くも恥ずかしげもなく「てんざん」と称しているのである。手許のヤマケイの山名事典を見ても、かくのごとき不敬罪みたいな名前をもつ山は広い日本でひとつしかない。名前だけなら日本三山といわれる富士山にも立山や白山にも負けていない。バブルの日本経済が「世界一の経済大国」と吹きまくっていた錯覚と似てなくもない。ここらの住民はとんでもない大法螺吹きなのではなかろか?
それでも私はこの山名は気に入っている。まぁいいではないか、世の親たちはとても美人とはいいがたい娘(赤ん坊の顔より自分たちの顔を見れば誰もがわかるはず!)に「麗子」とか名づけ、ぼんくらな息子にも「聡」とか名乗らせているのである。そんなものなのである。ここらの原住民のアタマが多少不自由であるとの非難は、甘んじて私が受けることにする。
山名の由来は調べてみると実はたいしたことではなかった。だがあえてここでは記さないことにする。そのほうが読者も興味が続くというものではないか。

登山経路案内
2000年代の経路は簡単である。車で頂上直下までいける。とくに1980年代に北面の山腹に北九州唯一の人工スキー場が開設されて道路が拡幅され、また、頂上直下に九州電力の揚水式発電所ができてからはその駐車場まで乗り入れて30分歩けば山頂に着ける。
ただしここで紹介するのは1960年代のルートである。ときは1965年の11月下旬の日曜日とでも設定しようか。
7時8分県庁前発唐津行きの昭和バスの約束で堀端の道を急ぐと、ようやく明るくなってきた朝靄の中で友だちが手を挙げている。吐く息は白い。バスの乗客は私たちだけである。小城のバスセンターの2つほど先の停留所である天山宮前で下車する。これが7時40分くらい。ここから農道を北へ歩く。みかん畑の中をてくてく歩いて、作業をはじめた選果場のつやつやひかるみかんがベルトコンベアの上を流れるそばを通る。天山下宮の石段下につくのが1時間後、ここでお茶でも飲もう。
ここから登りが始まる。車道をジグザグと3つほどきって、すぐ道の右にある小径に入る。急斜面の荒れた畑のあとを横切り、ガレ場をのっこす急登である。これが30分つづくと冬だけ開かれる川内分教場のそばに出る。ここから道はまた広くなるが、もう舗装はされていない。山頂がどんと真正面に現れる。道の傍らにはわさび田がつくられている。だらだら登った突き当たりに清冽な水が湧き出る沢がある。ここまでがバス停から2時間前後で、この水場では固形燃料で紅茶を沸かして飲む。
水場からもう少し作業用の林道を水平にたどり、急斜面の一面ススキの原を直登する。石ころの多い歩きづらい道である。ススキのトンネルをぽっと抜けると、石の祠とブロック建ての荒れた避難小屋がある天山上宮につく。水場からここまで50分、山頂まではあと40分となる。祠の前の池はたまり水で飲むことはできない。一休みして草原の中の道を頂上に登る。
登れば広闊な頂上からは360度の展望があり、佐賀平野の町々と緑の田園(この季節は刈り取りが終わって枯れ草と土の色か?)が見渡せ、蛇行して平野を流れる水のきらめきの果てにひときわ輝く有明海の水平線が眺められる。天気がよければ雲仙岳も見える。遠い阿蘇の噴煙も望めるとガイドには書いてあるが、これは(九州が沈没する大爆発までは)うそである。北は山々が幾重にも連なり、玄界灘や朝鮮半島は残念ながら見えないが、海を越えてくる風は感じることができる。草原の風に寝ころべば気分はきわめて心地いい。
山頂にある石碑は阿蘇惟直の墓である。1336年、九州に流れ着いた足利尊氏を筑前多々良浜に迎え撃った南朝の忠臣であるが、敗走して麓の小城で討たれたという。ふるさと阿蘇の噴煙が見えるところに葬ってくれとの遺言によってつくられたというが、それにしては立派すぎる。700年の時の流れに当時の私は感激していたものだったが、大人になって調べてみると皇国史観花盛りの戦前の時代に地元の青年団がたてたものだそうだ。なまじ事実を知ればロマンは吹っ飛ぶということか。
下りは山頂の稜線をたどって東に進み、彦岳との鞍部にある七曲峠へ降りて左に転ずる。少し下って瀬音がしたら、木をかきわけヤブこぎをして水場に出る。ここで焚き火を焚き、おにぎりをとりだし、インスタントラーメンをつくってわいわいと食べる。それが終われば沢の流れと連れ添いながら下る。天山の裏を縫う車道に出ると、あとは谷沿いの平坦な道が延々と古湯温泉まで続くだけである。
柿の実が真っ赤に色づいて夕陽に映えるのどかな山村の晩秋を、友だちときゃっきゃっと笑い転げながら歩く。すでに夕闇が忍び寄ってきた古湯の里からおくんちの笛と鉦の音が聞こえてくる。たおやかに躍る少女のお化粧した白い顔に、あざやかな口紅の色が空間を引き裂き、胸を衝かれる思いがする。温泉の共同浴場に入る。外にあるトイレに行くと女湯が硝子戸こしに幻のように浮かんでいた。
とっぷり暮れた道をバスに揺られて佐賀の町に帰るころには、せっかく山にいる間忘れていた焦燥感―このところまるで勉強していない―が、若い私にまた襲いかかってきた。

補遺
下山路はまだいくつかあって、七曲峠を右に降りると名瀑のある清水観音に出る。蛍で有名な祇園川に沿って歩けば、天山酒造や村岡羊羹の古い石造りの製造場がある。この道は小城のバスセンターに出る。
登ってきたススキの原を引き返し、水場と反対方向に川内集落を抜け右に転ずると明治佐賀炭鉱の炭住街に入り込む。この先に国鉄唐津線の中多久駅がある。
1964年から1967年までの3年間、つまり私の高校時代、この山には20回近く登った。朝な夕な北方に紫の山影を鎮める天山を眺めていると、山に登るとは天山に行くことと同義語であった。ちなみに登山口のバス停から山頂までの標高差は1020m、佐賀平野は海抜数メートルといったところだからそれなりの登り甲斐はあったのである。
高校を卒業して30年目である1997年の秋、Coming Home Dayのイベントで同級生たちと久しぶりに登った。所要時間は30分であったけれど、頂上のたたずまいも眺望も昔と変わることのないように思えた。
山は変わらないが私はすでに青春ではない。一名山とは、その山が特徴的なのではなく登る人間がどうであったかではないか。有力候補とするゆえんである。
(2001.4 記)